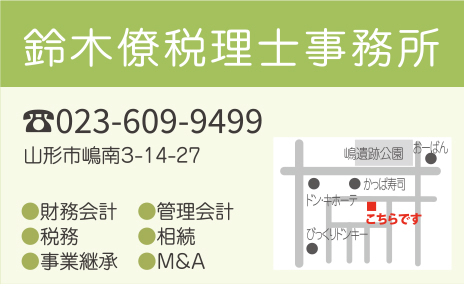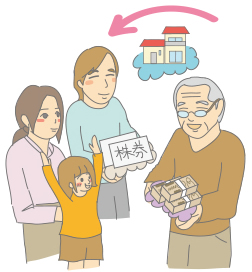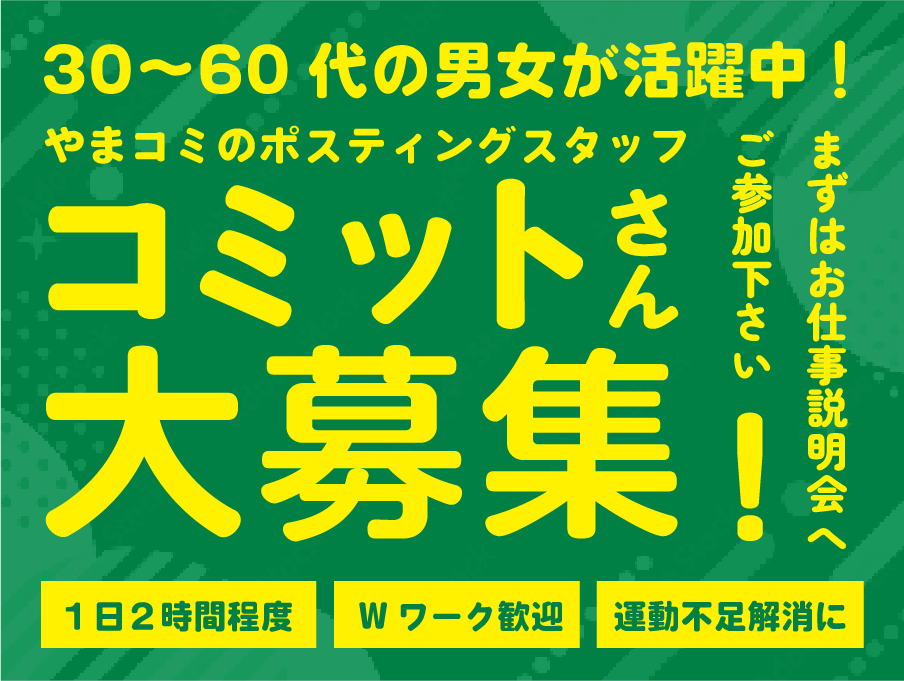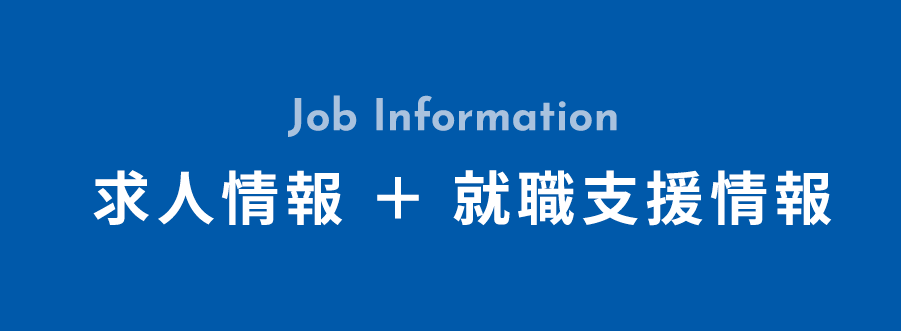相続の基礎知識/(67)住宅ローン控除
マイホームの新築や増改築の際に、金融機関から借り入れるお金が住宅ローン。
国は、無理のない負担で住宅を確保することを促進するため、「住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)」を用意。一定の条件を満たすことで、住宅ローンの年末残高の0.7%を所得税(一部は翌年の住民税)から最大13年間控除することができます。
◆ ◆

その住宅ローンを夫婦で組む場合、「ペアローン(夫婦2人とも主たる債務者)」と「連帯債務型(夫婦の1人が主たる債務者でもう1人が従たる債務者)」という2つの方法があります。
どちらも夫婦それぞれが住宅ローン控除を受けられるというメリットがありますが、「連帯債務型」の場合、事前に夫婦それぞれの支払い能力等をしっかりと把握した上で、連帯債務の割合を決めないと後々困ったことになりかねません。
例えば、次のようなケースです。
《ケース1》
連帯債務型でローンを組んだのに、返済はすべて夫の口座から支払っている。
《ケース2》
連帯債務の割合を夫70%、妻30%としたが、実際の住宅の共有割合が50%ずつになっている。
①の場合、ローンの返済はしていなくても、生活費は妻が負担しているとか、妻の債務割合分を夫の口座に預け入れているとかの合理的な理由があれば問題ありません。
ただしそうではない場合、①②ともに妻は夫から贈与を受けているとみなされる可能性があり、贈与とみなされた部分は住宅ローン控除を適用することができない可能性があります。
◆ ◆
住宅ローンは長期で組むことがほとんどですから、その間にライフスタイルが変わることもあるでしょう。
ただし、安易に住宅の共有割合を変更すると、不動産の贈与または譲渡を受けたとして、贈与税または譲渡所得税が発生する可能性がありますのでご注意ください。

鈴木僚税理士事務所 税理士
鈴木 僚(すずき りょう)
1988年(昭和63年)山形市生まれ。2018年に税理士資格取得。趣味はドライブ。