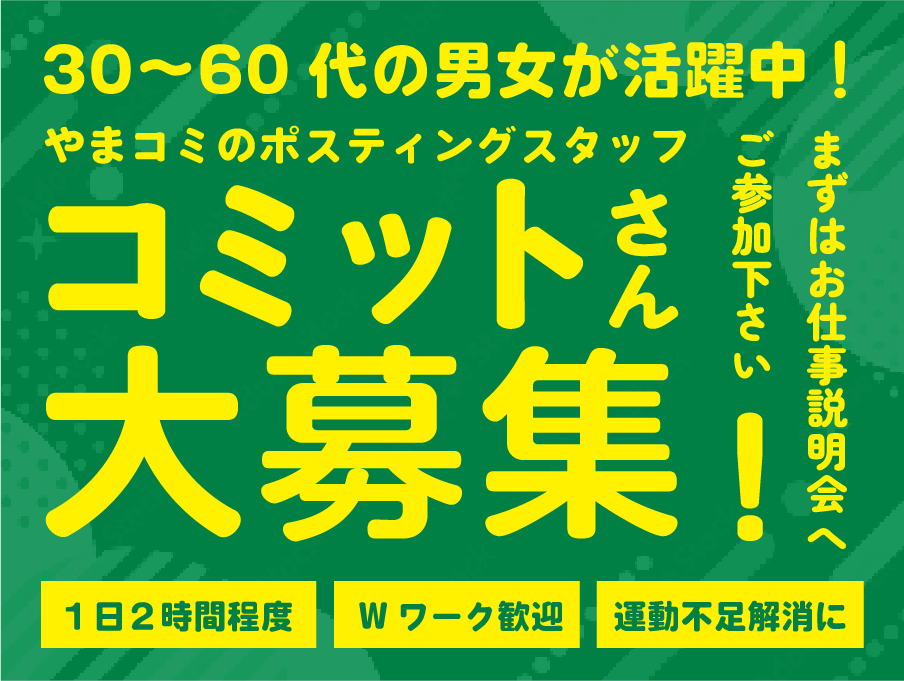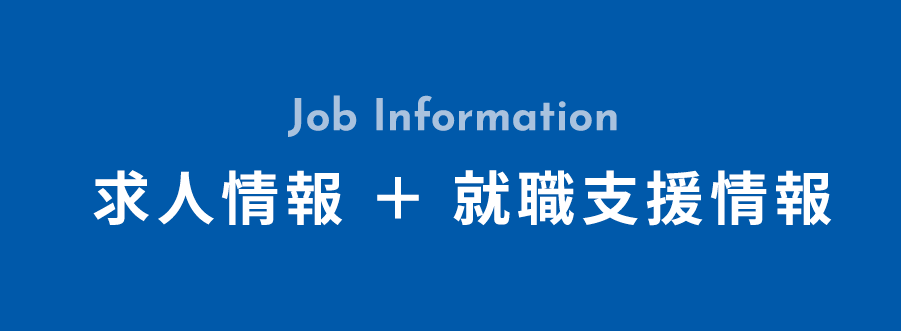セピア色の風景帖
《セピア色の風景帖》第189回 たばこ屋
「昭和」は喫煙者にとっては古き良き時代で、ほとんどの場所で喫煙が許されていた。

バスや列車の車内、待合室にも灰皿が用意され、映画館では充満する煙の中、映写の光の筋がはっきり浮かび上がるほどだった。歩行中や自転車に乗りながらの喫煙もそこかしこで見られ、路上には吸い殻が散乱していたのが日常だった。学校行事で配されたバスは例外なくヤニ臭く、多くの子どもが車酔いする原因になっていた。
当時、山形市周辺には専売店がほとんどなく、雑貨屋、酒屋、洋品店などの片隅にタバコを販売する窓口が置かれることが多かった。買ったタバコを吸いながら店先の赤電話をかけるサラリーマンの姿をよく見かけた。
後になって自動販売機が登場するが、並行して異業種による窓口販売も続けられていた。
「平成」に入ると、タバコの税収より健康被害にかかる予算の方が大きいとされ、タバコのCMは姿を消し、禁煙が叫ばれるようになった。
相次ぐ値上げで喫煙率は下がり、喫煙者の肩身は狭くなっていく。タバコ販売の主流はコンビニに移り、「令和」の今、街なかでタバコの窓口を備えた店を見かけることも少なくなった。(F)