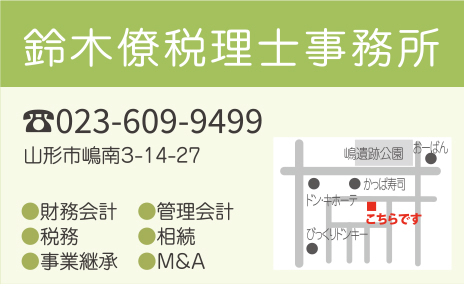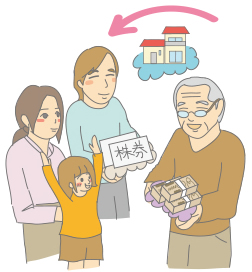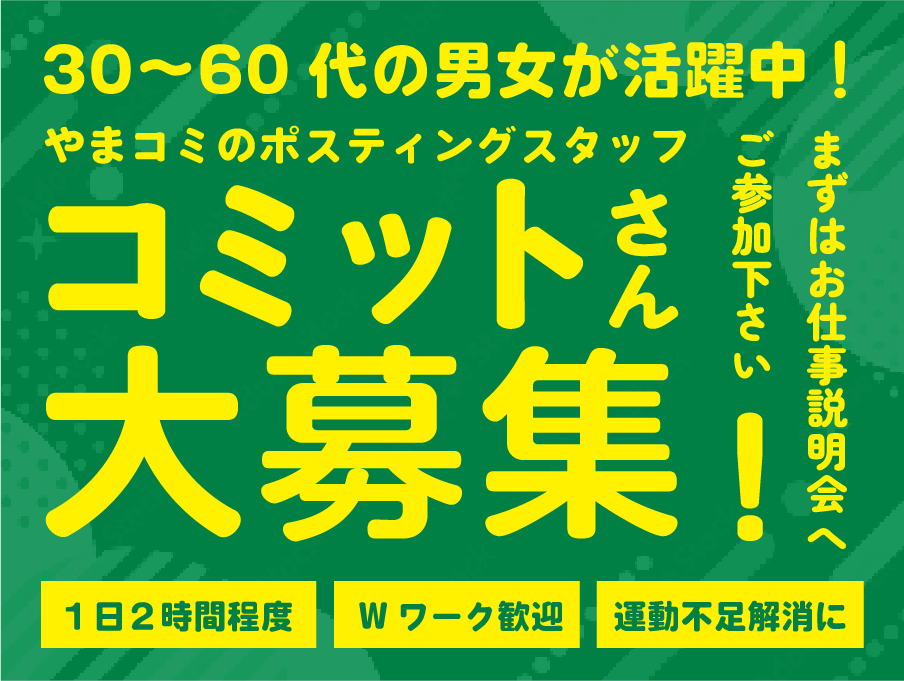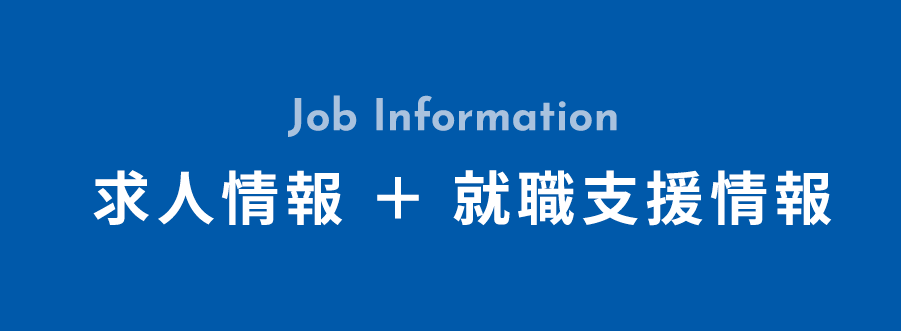相続の基礎知識/(66)保険金の確定申告
確定申告は、毎年1月から12月までの所得額とそれに対する所得税の額を計算し、その過不足を精算する手続きです。
主に個人事業主の方や給与収入が2000万円、副業所得が20万円を超える方が対象ですが、それ以外の人でも、生命保険(または共済金)の「満期保険金」や「解約保険金」を受け取っていたらご注意を。これらは贈与税や所得税が課税されるため、昨年受け取った場合は今年の3月17日までに確定申告をしなければなりません。
◆ ◆
「死亡保険金」も同様で、保険契約で次の①~③が誰であるかによって所得税や相続税、贈与税のいずれかの課税対象になり、確定申告が必要です。
①被保険者
②保険料の負担者
③保険金受取人
例えば夫が亡くなり、死亡保険金を一時金で受け取る場合で説明しましょう。
《ケース1》
①夫②妻③妻の場合
死亡保険金は妻の一時所得として所得税が課税されます。(ただし年金形式で受け取る場合は雑所得)
一時所得の金額は、受け取った死亡保険金から既に払い込んだ保険料または掛金の額を差し引き、さらに特別控除額50万円を差し引いた金額で、この結果が0円であれば課税されません。
ただし、ほかにも一時所得があれば、合算しなくてはなりません。
《ケース2》
①夫②夫③妻の場合
妻に相続税が課税されます。受取人が相続人である場合、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が適用されます。
《ケース3》
①夫②妻③妻以外の場合
妻以外(例えば子)の受取人に贈与税が課税されます。ただし死亡保険金が110万円以下であれば非課税なので申告義務はありません。同年にそれ以外に贈与があれば合算して判定されます。
◆ ◆
ところで、妻が手続きをした保険契約であれば、②は妻だと思いがちですが、保険料を夫の口座から支払っていた場合、②は夫が正解で、妻には所得税ではなく相続税が課税されます。
「満期保険金」や「解約保険金」も、①~③が誰なのかで判定されますが、複雑なケースがある点に注意しましょう。

鈴木僚税理士事務所 税理士
鈴木 僚(すずき りょう)
1988年(昭和63年)山形市生まれ。2018年に税理士資格取得。趣味はドライブ。